
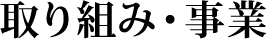

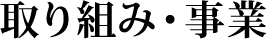
活動報告2025.10.29
2025年8月4日(月)~6(水)の三日間、サマーセッションにて社会連携フィールドワーク『引退競走馬のセカンドキャリア構築による人馬のウェルビーイング』を開講しました。全学共通教育プラットフォームにより全学部へ履修募集がなされ、15名が授業登録しての実施となりました。
本授業は、大学院特定課題研究所である『人馬のウェルビーイング研究所』(以下人馬WB研究所)が監修し、同研究所長であるスポーツ健康学部高見京太教授によって開講されました。
本授業については、2020年度より3期連続で「課題解決型フィールドワークfor SDGs」として開講され、昨年2024年度からは社会連携フィールドワークでの展開となり、計5期連続での実施となりました。フィールドワークを通じて「人馬のウェルビーイング」(以下人馬WB)の理念を基に、「引退競走馬のセカンドキャリア構築」の実現に向けた具体的な方策を理解し、体感することを主眼に置きました。
授業の構成は、まず初日に現役の競走馬を直に理解・体感するため、川崎競馬場での競馬観戦講義を実施し、競走馬の躍動する姿を間近で観察。人馬WB研究所の荒川昌久大学院特任研究員が、競馬及び競走馬について専門的に現場解説しました。
二日目には多摩キャンパス馬場において、引退競走馬のセカンドキャリアを築く「リトレーニング/グラウンドワーク」という手法を、体育会馬術部の柏村晋史監督が解説の上、部員と繋養している引退競走馬の実演により学習しました。同部で繋養している引退競走馬8頭は全て、人馬WB研究所及び同部が提携している、北海道新冠町の競走馬生産・育成牧場である錦岡牧場より寄贈された馬達になります。
加えて、人馬WBの手法による馬との触れ合いと引退競走馬の生態解説講義を、現代福祉学部の深野聡兼任講師が展開し、受講生たちが直接引退競走馬に触れ合う貴重な機会となりました。
二日目午後から三日目最終日にかけては、地方競馬全国協会の、騎手など地方競馬を担う人材を養成・訓練するための機関である地方競馬教養センター(栃木県那須塩原市、以下教養センター)を訪問しました。騎手候補生の訓練馬として活躍する引退競走馬を観察すると共に、その引退競走馬に支えられて研鑽を積む騎手候補生達の訓練現場を見学させていただきました。授業の最後には、引退競走馬を議題として騎手候補生と受講生がグループワークを行い、活発で大変意欲的な議論を深め、双方で実りある交流が出来ました。
授業終了後には各受講生より、「競馬というビジネスのなかでどうしても生まれてしまう引退馬は、競馬ファンとしても目を背けてはならない問題であり、今回のフィールドワークで業界の方々の意見を伺い、馬術部の皆様との交流を通じて、競馬ファンとして引退馬にどうやって向き合っていくか改めて考えるきっかけになりました。」、「川崎競馬場での競走観戦が印象に残りました。理由は、初めて生で馬が全力疾走をしている所を見れたからです。これまで自身に競馬観戦の経験があれば、別のプログラムが印象に残っていたかもしれませんが、初めて観戦した私にとって馬の上に人が乗って全力疾走している姿は圧巻でした。小さい頃にあの姿を見ていたら私も養成所の生徒の様にジョッキーを夢見ていたかもしれません。」、「引退競走馬のセカンドキャリアの社会的意義は、現在大学の馬術部で使用されていたり乗馬クラブで一般の人が馬に触れる機会を提供していたりする面から、より多くの人に馬や競馬、馬術について知ってもらうための役割を担っているところにあると考えます。今後の展望については、より多くの大学の馬術部が引退競走馬を受け入れ、そのことを宣伝したり、引退競走馬だけで開催しているイベントの告知をもっと大々的にすることが必要ではないかと考えました。 私自身、法政大学に馬術部があり馬を飼っていることは知っていましたが、その馬たちが普段よく見ている競馬の世界を引退した馬達であることは全く知らなかったので、そのような人が多いのではないかと感じます。そのためまず第一に今、競馬に興味を持っている層に対して普及活動をしていくのが良いのではないかと考えます。 多くの人が引退競走馬のセカンドキャリアに関心を向けてくれるようになれば、経済面で支援をしてくれる人が現れたり、今とは全く違うセカンドキャリアが構築されたりするのではないでしょうか。」、「人馬のウェルビーイングの実践が最も印象に残りました。触れ合う前に事前にネットで得た知識では、馬はかなり臆病で慎重に関わる必要があると書いてありました。しかし実際に触れ合ってみると落ち着いていて、中にはこちらに興味を示してくれる馬もいました。勿論全ての馬が同様に落ち着いているわけではなく、個性やそれまでの経歴によっても違いがあることは理解しているものの、この経験は馬への認識が良い方向へと変化する経験となりました。また、馬に触れる前に受けた講義の中で馬と人間の歴史を学習し、思っている以上に私達と近い存在であり、これまでの歴史を築いてきている動物であると学ぶことができました。この様な歴史は、小中学生の校外学習などで学ぶことができれば、とても良い経験になるのではないかと感じました。」、「特に印象に残ったのは、騎手候補生にとっての『馬の存在』に関する話でした。乗っているときは『先生』、世話をしているときは『友達』と表現されていて、更に馬毎に性格や顔や体の大きさといった特徴が違うため、接し方や世話の仕方、器具のつけ方も変わるという話を聞き、驚きとともに感動しました。正直それまで私は教養センターの馬を単純に練習のための馬のように考えてたので、この話は衝撃でした。馬に対する信頼がなければ、早朝からの世話や訓練に向き合えないはずで、人と馬に強い信頼関係がないと成り立たない世界なのだと実感しました。」、「特に騎手候補生との懇談が印象に残った理由として、馬や競馬に対して何の知識も持たず参加したフィールドワークでしたが、三日間を通して学んだ知識や感じた経験を、騎手候補生との懇談を経てブラッシュアップすることができました。私よりも年下の騎手候補生でしたが、しっかりしていると感じるような意見を持っていたことに加え、彼らならではの考え方や馬や馬術に対する姿勢を知ることができ、知見を広げる良い機会となりました。自分の将来をしっかりと見据え、夢に向かって日々精進する姿には見習うべきものがあると感じ、自身がこれまで馬の世界を知らなかったからこそ、彼らの世界を皆に知ってもらうことができたら良いなと感じました。」、「騎手候補生との懇談は、三日間のフィールドワークを通して学んだ知識や経験を振り返る良い機会となりました。また、彼らの馬に対する考え方に感心し、将来に期待を持ったことで、最初は今回のフィールドワークで終わると考えていた馬との関わりを、彼らや馬の活躍を目にする為にも続けていきたいと感じることができました。」、「馬と触れ合いたいという気持ちで参加した本授業ですが、未来の騎手達との懇談は想像以上に有意義で楽しいものでした。若くして厳しい練習に励み、アスリートとして競馬業界を引っ張っていく彼らの姿に深く感動し、強く応援すると共に、ますます競馬が好きになりました。」、以上の様に、実感の籠った熱心な感想が寄せられました。
本授業では、各専門家からの実践的な講義や、実際に馬達を間近で観察して直に接することで、『引退競走馬のセカンドキャリア構築による人馬のウェルビーイング』の実践知を得る機会となりました。
今後も人馬WB研究所として地域社会や行政、企業との協働を推進し、産官学連携の基で、引退競走馬を利活用した研究教育並びに授業を創出して参ります。
※地方競馬教養センターの騎手候補生の方が、本授業での交流について記事を作成していただきましたので、こちらもご覧ください。
https://www.keiba.go.jp/topics/2025/09/1012151384842.html(外部サイト)





